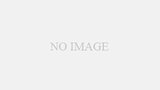1 預託料未払の実情
先日、調教師の先生と会わせていただくタイミングがありました。いろいろとお話を伺い、とても勉強になりました。
話の中で、競走馬の預託契約の話が出ました。聞いたところ、ごく一部馬主が、預託料の支払いを滞ってしまっているとのことでした。育成牧場や生産牧場への未払が生じているケースもあるようです。
出走手当で賄うことを考えていたもののけがをしてしまった場合や、馬主側のリサーチ不足でランニングコストを把握しきれていない場合などが原因のようです。
少なくとも月数十万円のお金になるうえ、遠征時の馬運車代や急な病気の時などで費用がかなりかさむこともあります。
その間調教師や牧場側が立替をすることになるわけですし、負担が小さくありません。資金繰りに影響を与える可能性もあり、厩舎の運営にもダメージを与えるものです。
2 対処法(代物弁済)
これに対応するためにもっとも有益な方法としては、代物弁済の予約をしておき、〇か月(あるいは〇円)の未払が生じた場合に、代物弁済を完結させる旨の意思表示をし、対象馬の所有権を調教師や牧場側が取得できるようにするものです。
まず、代物弁済の説明から行います。
代物弁済とは、ある債務に対して、お金ではなく物で支払いをするというもので、民法上も認められているものです(民法482条)。
代物弁済の要件は、①既存の債務があること、②①の債務の弁済に代えて、所有権を移転する旨の合意をしたこと、③②当時において、債務者が対象物の所有権を有していたこと、④②の合意に基づき、対象物を引き渡したこと、とされています。
馬の預託契約で言うと、①は預託料になります。
預託料の支払いを現金で行うのに代えて、馬という現物を交付するという合意を双方で行うこと(②)、当該合意時点において、馬主側に当該馬の所有権があったこと(③)、当該合意に基づいて馬を引き渡したこと(④)、が要件となるわけです。
このような合意を、未払になった馬主と協議をし取り付けることができればよいのですが、調教師や牧場側からすると交渉をしないといけなくなり、非常に手間が大きいです。
協議がまとまらないことも考えられ、その場合は未払だけかさむこととなります。
馬には罪がないので、その間も食べるものは食べさせることになると思いますし、最低限の世話はされているかと思います。非常に負担が大きい状態です。
3 代物弁済の予約
そこで、考えられる方法としては、預託契約において、代物弁済の予約をするというものです。
これは、「仮に将来、預託料等の債務が〇円or〇か月未払となった際に、調教師や牧場側が意思表示をすることで、代物弁済を完結することができる」という趣旨の合意を事前に行っておくというものとなります。
この形をとる場合の留意点は、以下のとおりです。
(ⅰ)あくまでも「代物弁済の予約」ということがわかるようにすること
(ⅱ)代物弁済の予約を完結させるという意思表示を明確に示すようにすること(予約完結権の行使)
(ⅲ)代物弁済により取得した馬は、その先第三者に売却されるのが通常ですが、その場合その売却代金が未払額を上回るのであれば、差額を馬主に返す必要があること
単に「未払の場合は馬を売却して清算する」との規定にとどまると、当該規定の法的性質をめぐって争いになる可能性が否定できません。そのため、性質を確定させるために、代物弁済の予約である旨を明確にすることをお勧めします。
また、所有権を移す場面になるので、その証拠は慎重に残す必要があります。清算に関しても、その金額や充当関係が明確になっているような書類を残すことも重要です。
あまり考えたくはないですが、馬主側が破産や差押えを受けた場合など、第三者との間で先後関係が問題になるケースも考えられるため、内容証明郵便の活用や、確定日付の取得を行うことも重要となります。
以上のとおり、預託契約においては代物弁済の予約の規定を設けておいたうえ、未払が累積する場合には予約完結権を行使し、馬の所有権を取得、売却して預託料を回収するという形が、調教師や牧場側の自衛策として考えられます。
馬主側としては、当該条項は不利になりますので受け入れるか否か、受け入れるとして、その未払の金額や期間のラインをどのようにするか、というところがポイントになりますね。
なお、日本軽種馬協会が出している、繫殖牝馬の預託契約書のひな形には代物弁済の予約ができる規定が盛り込まれております(https://jbba.jp/data/booklet/ 参照。)。
生産・育成牧場においては、このひな形を活用して契約を締結するのが望ましいですね。
調教師においては、調教師会などでひな形を用意しているかと思いますが、その内容について、改めて精査するのがよいですね。
また、まったく別の方向性としては、いくらかお金を先に預かっておくというのも考えられます。賃貸借契約時の敷金に似た発想です。
ただ、このような形は一般的にとられておらず、提案した際に、馬主側から預託を断られるケースも考えられるところです。考え方としてはありうるものの、現状には即していないような気がします。
4 弁護士に依頼すべきポイント
契約書の作成(ひな形及び当該事案に応じたもの)は弁護士の重要な業務の一つです。
今回触れた代物弁済の予約以外にも規定すべき条項、注意すべき条項は多々あります。
トラブル回避をしたい、過去にトラブルにあって痛い目にあってしまった、という方は、町の巡回無料相談などでも構わないので、一度弁護士に相談し、預託契約書を見直してみるのが良いかと思います。
その際には現行の契約書のひな形を持っていくと話がスムーズに進みます。
また、実際問題、代物弁済という形で処理を行うことができない場合も想定されるところです。
代物弁済で調教師や牧場側が馬の所有権を取得したとしてもそれだけではお金にならず、馬を第三者に売却して初めてお金となります。
その手間もありますし、そもそも満足な価格が付かない馬である場合も起こりうると考えられます。
そういった場合においては、別途債権回収のために、裁判所の手続きなどを活用することになると考えられます。
ここまでくるとハードルが上がるうえ、時間も労力も割くことになりますので、弁護士への相談をするのが良いと思います。
次回以降、他の条項や、JBBAが出しているひな形につき、解説を行っていこうと思います。
ぜひ、馬産地にて参考にされることを期待しております。